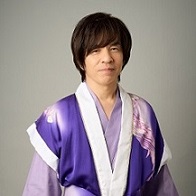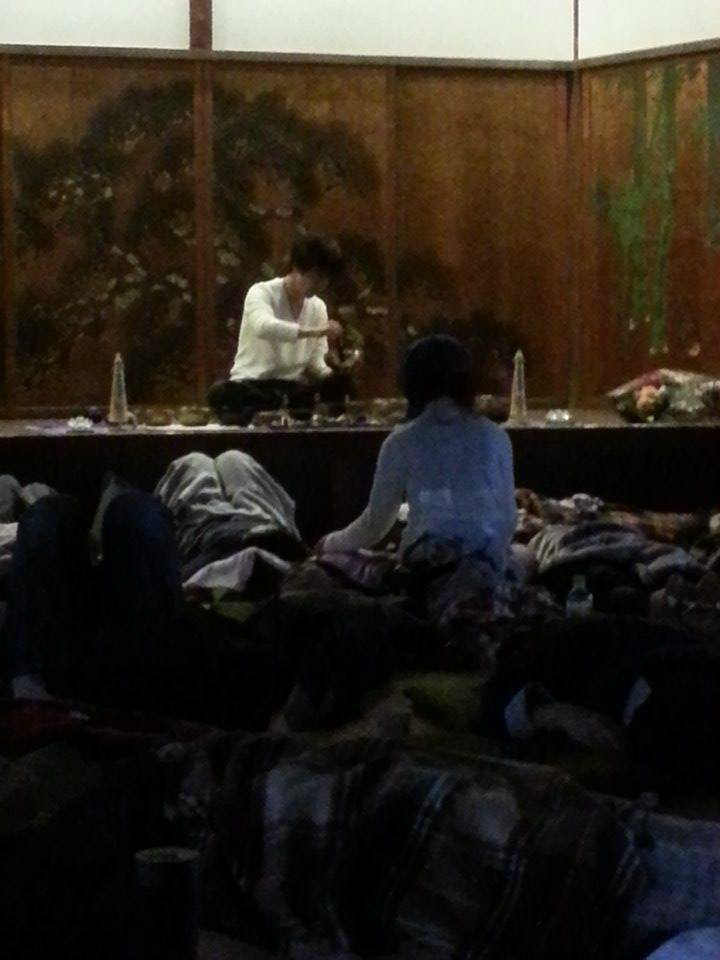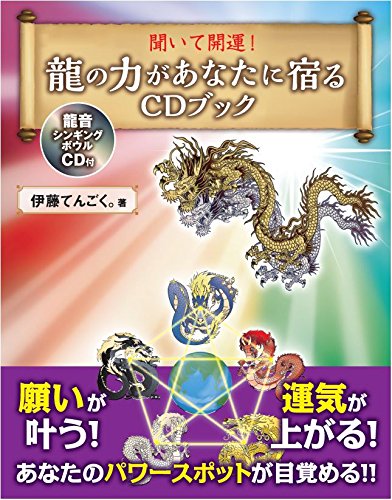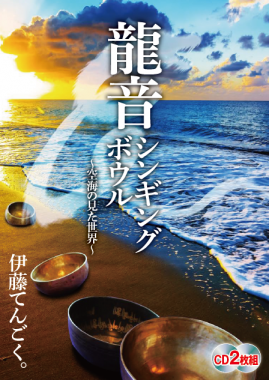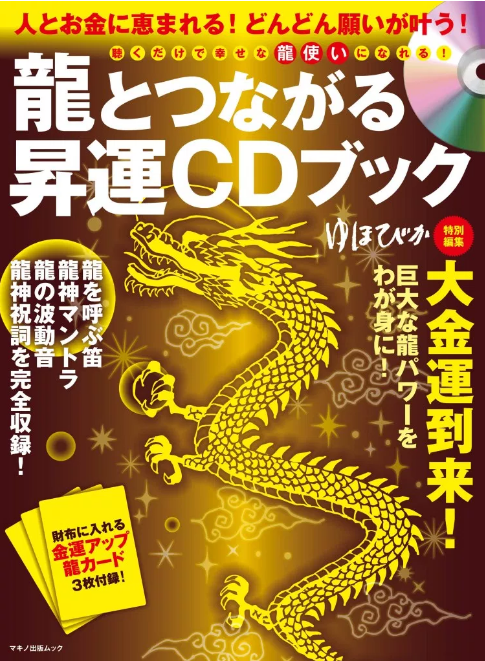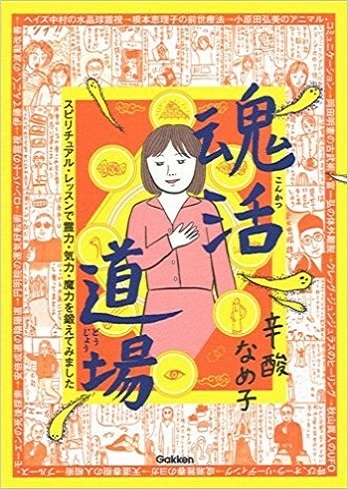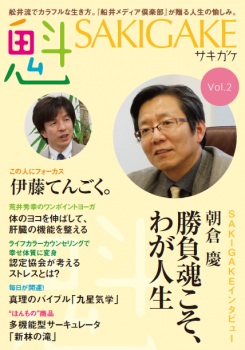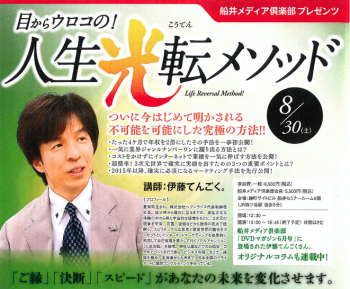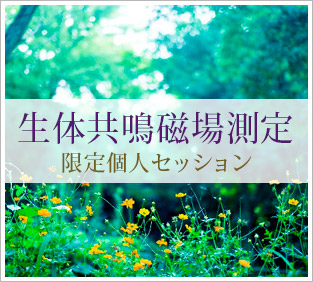2009'04.10 (Fri)
筑前一之宮 住吉神社
住吉神社は全国に2129社あり、その本社は現在、大阪の住吉大社ですが、
もっとも古く、その元となるのが、この博多住吉神社と言われています。
その歴史は1800年にもなります。

住吉神社のご祭神は、公式HPによると、底筒男神(そこつつのおのかみ)、
中筒男神(なかつつのおのかみ)、表筒男神(うわつつのおのかみ)の3柱を
住吉三神としています。
御出現は、伊弉諾大神(いざなぎおおかみ)が筑紫の日向の橘の小戸の
阿波伎原でミソギハラヘ(禊祓)をされたときにお生まれになったと「古事記」に
記されています。
相殿(あいどの)には天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)、神功皇后(じんぐう
こうごう)を配祀し、これを併せて住吉五所大神とも呼ばれています。
住吉神社の御神徳は、ミソギハラヘの御出現の由来から、「心身の清浄」を以て
すべての災から身を護る神として古より広く信仰されています。
また、つつのお(筒男)の「つつ」には星の意味があると云われ、航海・海上の
守護神としても厚い崇敬があります(以上公式HPより抜粋)。

伊勢神宮は20年に1度、式年遷宮(神殿を新しいものに作り変えること)が
行われますが、この住吉神社は25年に1度、国の重要文化財でもある本殿を
中心に式年遷宮が行われます。
いよいよ来年、平成22年がその遷宮の御年となり、10月に遷宮が行われます。
天皇家ゆかりということもあって、神門には、菊の御紋がありました。

この日は雨でしたが、神官が祝詞をあげると、神域はスピリチュアルな雰囲気に
包まれました。

良く見ると、本殿の向かって左端の木の上に、縦に、本殿の屋根にかかるように、
細い光の筋のようなものが写っていますね。
今は都心にありますが、その昔、この住吉神社は河口に、海に向けて建てられて
いたと古書には記載があります。
つまり1800年前は、博多駅(当然駅はありませんけど・・・笑)のあたりまで海であり、
福岡ドームや現在の繁華街 天神、中洲 は海の中だったということですね。
さて、1000年後はどうなっているんでしょうね~。
生まれ変わったら、また行ってみようっと。笑
今日もご覧いただき、ありがとうございます。
訪れて頂いたみなさんに幸せの光が降り注ぎますように。
下記のランキングに参加しています。
皆さんの応援がこのblogのエネルギーになり、次の記事へとつながります。^o^
ぜひ、下記バナーをクリックお願いします。





こころより感謝いたします。ありがとうございます。 m(_ _)m
2009'04.03 (Fri)
福岡天神、水鏡天満宮

福岡天神、繁華街の一角、アクロス福岡のすぐ前に水鏡(すいきょう)神社、
通称水鏡天満宮、または水鏡天神と呼ばれる神社があります。
福岡の繁華街 ”天神” の名前はこの神社にちなむものであり、この神社の
存在感を表しています。
遠い昔、901年、学問の神様といわれる菅原道真が大宰府に赴任する途中、
四十川(しじゅうかわ)に姿を映して水鏡にしたと言われ、そこに社殿が建ち、
容見(すがたみ)天神または水鏡天神と言われました。
江戸時代になると、藩主黒田長政がこの地に天神さまを移しお祀りしたことから
このあたりが ”天神”と呼ばれるようになり、現在の繁華街の名前の由来と
なっています。

この鳥居にある「天満宮」の額は、福岡出身の元総理大臣 広田弘毅 の、小学生の
時の書と言われています。
小学生の時に書いた書が 神社の鳥居の額になるって どういうことなんでしょうね~。
すごいことですね。
広田弘毅は、作家 城山三郎の 『落日燃ゆ』 という小説の主人公ともなった人です。

天神様だけに、境内には狛犬だけではなく、牛さんもいました。
なんだかここだけゆっくりと時が流れているような異空間となっています。
都会のオフィスビル街の喧騒を忘れさせてくれる、都会の小さな天神様は今も
天神の街を静かに見守っています。
今日もご覧いただき、ありがとうございます。
訪れて頂いたみなさんに幸せの光が降り注ぎますように。
下記のランキングに参加しています。
皆さんの1クリックがこのblogのエネルギーになり、次の記事へとつながります。^o^





こころより感謝いたします。ありがとうございます。 m(_ _)m